肥後医育塾公開セミナー

令和7年度 第1回公開セミナー「進化する診断テクノロジーの世界」

|
【司会】 肥後医育振興会副理事長熊本大学名誉教授 片渕 秀隆 氏 演題:座長挨拶 |
講演内容を見る |

肥後医育振興会副理事長熊本大学名誉教授
片渕 秀隆 氏
演題:座長挨拶

|
【座長】 熊本大学病院長・放射線診断学講座教授 平井 俊範 氏 演題:座長挨拶 |
講演内容を見る |

熊本大学病院長・放射線診断学講座教授
平井 俊範 氏
演題:座長挨拶
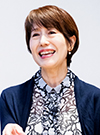
|
アナウンサー 福島 絵美 氏 |
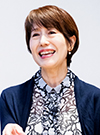
アナウンサー
福島 絵美 氏

|
肥後医育振興会理事長熊本大学名誉教授 松下 修三 氏 |

肥後医育振興会理事長熊本大学名誉教授
松下 修三 氏

|
【講師】 熊本大学大学院先端科学研究部情報・エネルギー部門ビッグデータ分野教授 尼﨑 太樹 氏 演題:【講演1】医療革命の入り口に立つ人工知能技術 |
講演内容を見る |

熊本大学大学院先端科学研究部情報・エネルギー部門ビッグデータ分野教授
尼﨑 太樹 氏
演題:【講演1】医療革命の入り口に立つ人工知能技術

|
【講師】 熊本大学生命科学研究部放射線診断学准教授 中浦 猛 氏 演題:【講演2】画像診断へのAIの最近の応用 |
講演内容を見る |

熊本大学生命科学研究部放射線診断学准教授
中浦 猛 氏
演題:【講演2】画像診断へのAIの最近の応用

|
【講師】 熊本大学病院病理診断科教授・部長 三上 芳喜 氏 演題:【講演3】細胞から病気を診る-変わりゆく病理診断 病理診断に最新技術活用 |
講演内容を見る |

熊本大学病院病理診断科教授・部長
三上 芳喜 氏
演題:【講演3】細胞から病気を診る-変わりゆく病理診断 病理診断に最新技術活用

|
【講師】 熊本大学生命科学研究部法医学講座教授 佐野 利恵 氏 演題:【講演4】法医学がひらく未来 |
講演内容を見る |

熊本大学生命科学研究部法医学講座教授
佐野 利恵 氏
演題:【講演4】法医学がひらく未来
第85回肥後医育塾公開セミナーが7月13日、熊本市中央区の熊本市医師会館で開催され、約100人が聴講した。年間テーマ「近未来の医療予想図をウオッチ:AI時代の最先端医療」の3回シリーズの1回目。今回は「進化する診断テクノロジーの世界~医療現場の今と未来~」と題し、4人の医師や専門家が登壇した。主催は公益財団法人肥後医育振興会、一般財団法人化学及血清療法研究所、熊本日日新聞社。

セミナー後半でファシリテーターに福島絵美さんを迎え、聴講者の質問に講師が答える形でクロストークを行った。
Q 希少がんの患者です。AIの進歩により、全国どこでも同じ水準の診断ができますか。
A 希少がんについて、画像診断でAIがどれくらい役に立つかというと今の時点では難しいです。将来的には手助けしてくれる可能性はあると考えています。(中浦)
Q もしAIが間違った判断をした場合、人間はどれだけ訂正できますか。
A その判断から実行までどのくらい時間がかかるかによります。時間がある程度あれば、人がAIの判断を本当に合っているかどうかをもう一度吟味するというのは可能だと思います。(尼﨑)
AIと医師が協働することによって、より提供できる医療の質が高くなると思っています。もちろん現状では、医療行為は医師の専権事項です。最終的な判断、責任は医師が負うという状況は続くので、心配はないと思います。(三上)
Q 医師でなく、AIの判断でロボットによる手術が行われるような状況が今後予想されますか。
A AIには「ブラックボックス問題」があります。AIがなぜそう判断したのかが分からない、人間みたいに説明できないという問題です。これだと医療安全的に「このようなことが起こったので、それを防ぐためにこの仕組みを作る」というのが非常に難しくなります。ですから、AIの判断を基にロボットが手術をするという世界はすぐには来ないのではないかと思います。(中浦)
Q 現在の診療の現場でAIの診断というのはどのくらい利用されていますか。
A 病理診断に関しては、まだ研究的な側面が濃厚で、実際に診断の現場で導入しているということはほとんど聞きません。組織が良性か悪性か、Aというがんか、Bというがんなのか、というシンプルなものであれば、AIは素晴らしい答えを出してくれると思いますが、病理診断では画像も含めさまざまな情報を収集した上で最終判断しなければなりません。(三上)
法医学においては、AIはほぼ導入されていない実情があります。亡くなられた方の所見が時々刻々と、ケースバイケースで変わるので、その状況をどれだけAIに落とし込めるかというところで、すごく課題があります。診断には解釈が入りますので、複数の視点から診断することが望ましいと考えています。(佐野)