すぱいすのページ
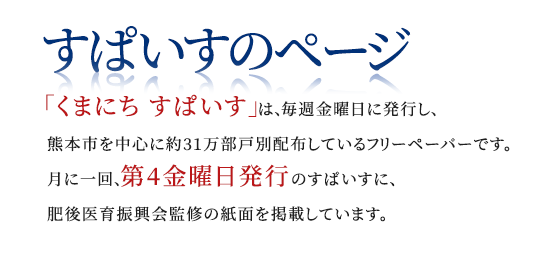
すぱいすのページ
「あれんじ」 2011年11月5日号
【四季の風】
第15回 虫を聞く会
| めぐりくる季節の風に乗せて、四季の歌である俳句をお届けします。 |
| よき酒もあり虫聞きに来よといふ 中正 |
|
俳句で「虫」といえば、秋によく鳴く虫のことで、秋の季語。虫の声にひかれて外歩きすることを「虫聞(むしきき)」といって、平安時代からの風流な遊びで、江戸の町でもよく出かけたものである。虫の声は、ときに賑やか、ときにあわれ。日本人は虫の音が好きだ。 |
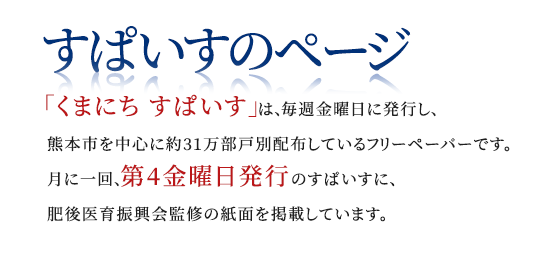
【四季の風】
第15回 虫を聞く会
| めぐりくる季節の風に乗せて、四季の歌である俳句をお届けします。 |
| よき酒もあり虫聞きに来よといふ 中正 |
|
俳句で「虫」といえば、秋によく鳴く虫のことで、秋の季語。虫の声にひかれて外歩きすることを「虫聞(むしきき)」といって、平安時代からの風流な遊びで、江戸の町でもよく出かけたものである。虫の声は、ときに賑やか、ときにあわれ。日本人は虫の音が好きだ。 |