すぱいすのページ
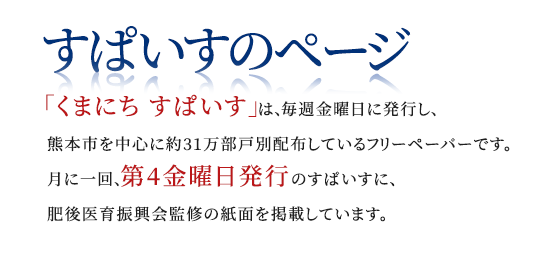
すぱいすのページ
「あれんじ」 2011年5月7日号
【四季の風】
第13回 滝
| めぐりくる季節の風に乗せて、四季の歌である俳句をお届けします。 |
| 今生(こんじょう)を滝と生まれて落つるかな 中正 |
|
「滝」は夏の季語だが、毎年五月、矢部の「五老ヶ滝」に吟行している。私は、若葉が萌えあがるころのこの古い里が大好きだ。 |
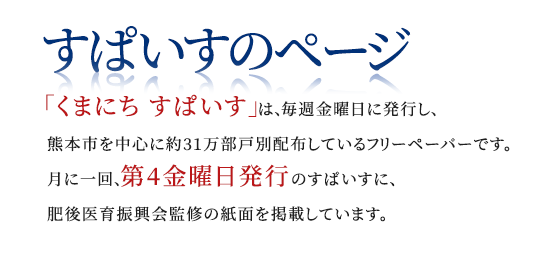
【四季の風】
第13回 滝
| めぐりくる季節の風に乗せて、四季の歌である俳句をお届けします。 |
| 今生(こんじょう)を滝と生まれて落つるかな 中正 |
|
「滝」は夏の季語だが、毎年五月、矢部の「五老ヶ滝」に吟行している。私は、若葉が萌えあがるころのこの古い里が大好きだ。 |