すぱいすのページ
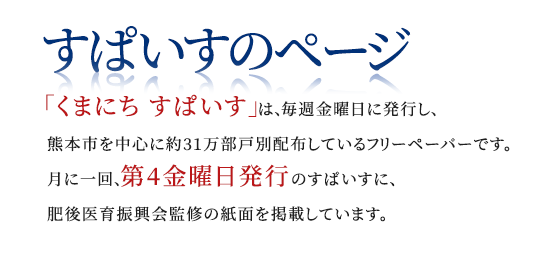
「すぱいす」 2025年7月号
【元気の処方箋】
手足口病、ヘルパンギーナ、咽頭(いんとう)結膜熱 「子どもの三大夏風邪」に注意
| 「手足口病」「ヘルパンギーナ」「咽頭結膜熱」は、夏に子どもを中心に流行する感染症です。夏休みで外出することが多いこの時季、これらの「三大夏風邪」に注意したいものです。病気の特徴や対処法について、熊本大学病院小児科特任教授の松本志郎さんに聞きました。 (取材・文=坂本ミオ イラスト=はしもとあさこ) |
| 話を聞いたのは |
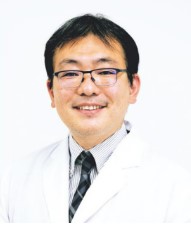
熊本大学病院新生児学寄附講座特任教授(小児科兼任)
松本 志郎さん 日本小児科学会専門医・指導医 |
| 【はじめに】感染症は夏にも流行 |

「感染症」と聞くと冬にはやるイメージがありますが、一部のウイルスは高温多湿の夏季に感染が拡大しやすくなります。 |
| 【1.手足口病】 |

●手のひら、足の裏、口の中に発疹 |
| 【2.ヘルパンギーナ】 |

●突然の高熱と喉の奥に強い痛み |
| 【3.咽頭結膜熱(プール熱)】 |

●熱や喉痛、目の充血、目やになど |
| 三大夏風邪の治療と対策 |
|
予防は手洗い、うがいが基本 |